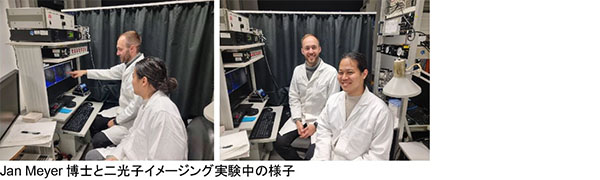トピックス
2025年2月28日
Research Stay at Heinrich Heine University Düsseldorf
2024年9月から12月までの3か月間、ドイツのデュッセルドルフにあるHeinrich Heine University Düsseldorf(以下、HHU)に研究留学を行い、Christine Rose教授の研究室において国際共同研究を実施しました。デュッセルドルフはドイツ西部のノルトライン=ヴェストファーレン州の州都で、人口は約60万人ほどの都市です。人口や面積は仙台よりも小さいものの、市街地の中心部はどこか仙台と似た雰囲気があると感じました。金融・経済活動が盛んで、日本企業の欧州拠点も多数存在し、ヨーロッパでも有数の日本人街が形成されています。そのため、日系スーパーや日本食レストランも数多くあり、海外でありながら日本文化を感じることができる土地といえるでしょう。また、市の中心部には歴史ある石造りの建築物と近代的なガラス張りの建物が混在しており、街並みを散策しているだけでも飽きることがありません。交通機関も地下鉄やトラムが充実していて、街の中心部から大学へのアクセスも非常に良好でした。
滞在中はAirbnbを利用して、市の中心部にあるアパートを借りました。徒歩数分圏内に市場や商店街、美術館、公園などが点在しており、日常生活を送るには非常に便利な環境でした。大学へは毎朝トラムで通学しましたが、チケットの購入や時刻表の確認にはドイツ語が必要な場面も多く、英語が通じるとはいえ細かい手続きには苦労しました。それでもラボのメンバーのサポートのおかげで、スムーズに生活を始めることができました。また、滞在したラボでは週末に動物実験が行えず、平日も長い時間は実験が行えない場合もあったため、余暇を利用して美術館を巡ったり、公園を散策したり、市場に出かけてさまざまな料理を楽しんだりと、余裕のある生活スタイルを満喫しました。
市内の市場やスーパーには、生の豚挽肉を使った“Mett”や、浅く塩漬けした生のニシンをはさんだパン、アルトビールなど、日本ではあまり見かけない料理が数多く並んでおり、毎日のように初めての味わいを楽しむことができました。さらに、街の立地上、ケルンへは電車ですぐ移動できるうえ、オランダのアムステルダムへも3時間ほどで行くことが可能です。休日を利用してこれらの都市を訪問する機会にも恵まれ、異なる街並みや文化に触れることができました。また、滞在していたアパートは市の中心部にあったため、12月には至る所で開かれるクリスマスマーケットをラボのメンバーとともに楽しむことができ、グリューワインや地元の名物料理など、ドイツ特有の冬の風物詩を満喫することができました。
滞在先の研究室は国際色が豊かで、英語とドイツ語の両方が日常言語として使われていましたが、研究室内だけでなく大学全体でもドイツ人学生・研究者が大半を占めていました。私が滞在したラボは顕微鏡を用いたイメージング技術に強みをもち、顕微鏡光学系の組み立てやメンテナンスに関するノウハウも豊富に蓄積されていました。日々の会話や実験の合間に得られる知識が非常に多く、常に新たな発見がありました。昼食時には、ポスドクから大学院生までほぼ全員が一斉に休憩室に集まり、サイエンスに関するディスカッションから、ドイツの文化・食生活にまつわる談笑まで、さまざまな話題で盛り上がりました。日本では少ないヴィーガンやベジタリアンの方もいて、食や動物実験に関する倫理観をシェアし合う機会も多く、そうした多様な価値観に触れることにより新たな発見や視点を得られました。
実施した共同研究内容としては、主にJan Meyer博士のサポートを受けながら、マウスの急性脳スライス切片を用いたアストロサイト・シグナル発生メカニズムの検証を行いました。切片内の細胞に蛍光センサーを導入し、アストロサイトの活動を計測するとともに薬理学的操作による制御実験を実施しました。HHUでは動物実験に関する倫理観が非常に厳格で実験用動物は管理施設の専任スタッフによって飼育され、研究者のもとに届けられた後は動物へのストレスが最小限となるよう、ごく短時間のうちに実験を終わらせることが義務づけられています。そのため、実験に割ける時間は日常的に制限があり、一度に大量の実験をこなすことは難しくなります。一方でこの厳格な倫理観の下で行われる研究環境に身を置いたことで、研究における動物への配慮を最優先に考え、実験をできる限り迅速かつストレスの少ない方法で進めるという考え方の重要性を再認識しました。こうした厳格な倫理観に基づく動物福祉への徹底した配慮は、生命を扱う研究者としての責任を強く意識させられるものでした。また、このような環境では研究者はワークライフバランスが取りやすく、研究者個人の生活の質を高める仕組みにもつながっていると感じました。夕方には家に帰って趣味などでリフレッシュするだけでなく、興味のある論文をじっくりと読む時間も十分に確保できるため、研究の視野がさらに広がると感じました。
実験記録やデータ管理に関しても興味深い点がありました。HHUではクラウド上で実験記録やデータの保持を行うことが奨励されており、私が滞在した研究室ではeLabという電子実験ノートのシステムを導入していました。これはクラウドベースのプラットフォームで、実験計画や実験記録を一元的に管理することができます。従来の紙媒体での実験ノートによる記録よりもデータの追跡や共有が容易になるだけでなく、研究の透明性や再現性を高めることにも役立つと感じました。
総じて、デュッセルドルフでの3か月間は、異なる文化や価値観に触れながら研究活動を進める貴重な経験でした。日本の大学や研究環境との違いを実感しつつ、それらの違いが必ずしも障壁になるのではなく、新しい発想やライフスタイルのヒントをもたらしうることを学びました。多国籍なメンバーと自由闊達に意見交換を行い、研究だけでなく日常生活においても新鮮な発見や学びが多かったです。ワークライフバランスを大切にしながらも先端的な研究を行う姿勢や、厳格な倫理基準に基づきつつも効率よく実験を進めるドイツの研究室のあり方は、今後の自分の研究スタイルにも活かせると感じています。今回の留学で得た知識と経験を活かし、今後も国内外の研究者との共同研究や情報交換を続け、より質の高い研究成果を目指します。
2024年12月
東北大学大学院 生命科学研究科 超回路脳機能分野 D3
山尾 啓熙